1.深刻化する”入口のすれ違い”と給与をめぐる誤解

外国人労働者の受け入れが急速に進む中で、雇用の初期段階での説明不足や誤解が原因となるトラブルが社会問題化している。
給与条件の認識の相違、勤務時間の食い違い、就業規則の理解不足など、いずれも”入口のすれ違い”が根本原因となり、本来築けるはずの信頼関係が早い段階で崩れてしまうケースが後を絶たない。
こうした問題は、単に個別企業の問題にとどまらず、外国人労働者の定着率低下や、日本の労働市場全体への信頼失墜にもつながりかねない深刻な課題となっている。
特に技能実習制度や特定技能制度を通じて来日する外国人労働者の多くは、母国での生活基盤を捨て、家族と離ればなれになりながら日本での就労を選択している。
彼らにとって、雇用条件や就業環境は単なる労働契約を超えた、人生をかけた重要な選択の基盤となる。それだけに、入口での説明が不十分だったり、誤解を招く表現があったりすると、その後の就労生活全体に深刻な影響を与えることになる。
外国人雇用におけるトラブルの中でも、特に深刻なのが給与条件をめぐる誤解である。長年中小企業の労務顧問を行っており、外国人労働者の雇用課題に直面した経験のある社会保険労務士の青木二朗氏は、この問題の根深さを指摘する。
「例えば『月給30万円』と説明されたとき、それが手取りか額面かをはっきり伝えないと、必ずといっていいほどトラブルにつながります」と青木氏は警鐘を鳴らす。
日本で働いた経験がない外国人労働者の多くは、日本の複雑な社会保険料や税金の仕組みに馴染みが薄い。厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、さらには所得税や住民税など、給与から控除される項目は多岐にわたる。
特に、住民税は入国翌年から課税されるため、2年目に突然手取り額が減少し、「契約条件が一方的に変更された」と誤解されるケースも珍しくない。
実際に、青木氏が顧問を務める企業では「面接時に聞いていた給与額と実際の振込額が大きく違う。会社に騙された」といった外国人労働者からの不満の声が上がることがあるという。
特に深刻なのは、母国の家族への仕送りを前提として来日している労働者のケースで、予想より少ない手取り額によって生活設計が根本から狂ってしまい、結果として失踪や転職につながることもある。
「『思っていたよりも振込額が少ない。説明と違う』という不満は、単なる金銭的な問題を超えて、会社に対する不信感に発展します」と青木氏は指摘する。
このような条件の食い違いは、労働者のモチベーション低下、職場の人間関係悪化、ひいては生産性の低下という形で企業側にも大きな損失をもたらすことになる。
2.法的義務を超えた丁寧な説明と言語対応の重要性

労働基準法第15条では、雇用時に賃金、労働時間、就業場所、業務内容などの重要な労働条件を文書で明示することが義務付けられている。
現在では、インターネット上で雇用条件通知書のひな形を簡単にダウンロードでき、控除項目や社会保険加入状況なども含めて比較的容易に作成することが可能だ。
しかし、青木氏は「法的な書面を渡すだけでは不十分です」と強調する。
「重要なのは、どの名目でいくら控除されるのか、なぜその保険への加入が必要なのか、控除された保険料が将来どのような形で本人に還元されるのかまで、丁寧に説明し、相手に理解してもらうことです」。
特に、厚生年金については、将来の受給権や脱退一時金の仕組みについても説明が必要だという。
また、青木氏は労働条件の説明だけでなく、職場のルールや文化についても十分な説明が必要だと指摘する。
「外国人であっても日本人であっても、全ての労働者に就業規則や社内ルール、さらには日本の職場文化の特徴について理解してもらう必要があります」。
残業の考え方、有給休暇の取得方法、報告・連絡・相談の重要性、チームワークの概念など、日本人にとっては当たり前でも、異なる文化背景を持つ外国人には理解が困難な要素は数多く存在する。中には「日本語が十分に伝わらないから詳細な説明が難しい」と感じ、最小限の説明にとどめてしまう企業も少なくない。
しかし、青木氏はこうした対応こそが後に大きなトラブルを招く原因になると警告する。
「言語の違いを理由に説明を省略することは、結果的に企業にとってより大きなリスクを生み出すことになります」。
言語の問題については、最近では様々な解決策が登場している。翻訳アプリの活用、多言語対応の就業規則作成支援ツールの利用、通訳サービスの活用など、技術的な解決手段は確実に充実してきている。
例えば、規則作成支援ツールの中には中国語やベトナム語の翻訳機能を実装するものも登場しており、企業の多言語対応を支援している。こうした動きの背景には、外国人労働者の定着率向上を重視する企業の意識変化がある。人手不足が深刻化する中で、採用した外国人労働者に長期間働き続けてもらうことの重要性が広く認識されるようになった。
短期的な採用コストの削減よりも、長期的な定着率の向上の方が、結果的に企業にとって大きなメリットをもたらすという考え方が浸透しつつある。
3.企業の主体的責任と組織改善のチャンス
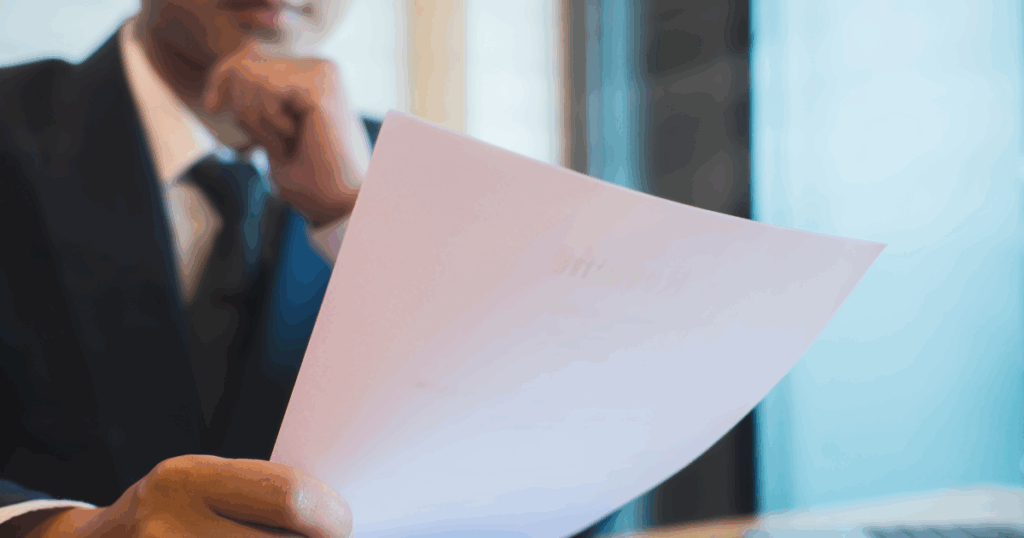
就業ルールの説明や雇用条件の明示は、本来企業が主体的に行うべき基本事項である。
しかし、実際の現場では「監理団体や登録支援機関に任せていれば大丈夫」と考えてしまう企業も少なくない。こうした企業からは、「雇用前の説明が不十分だった」「制度の詳細を後から知って困った」「思っていた以上に手続きが複雑で対応しきれない」といった不満の声も聞かれる。
この点について青木氏は明確な立場を示している。
「監理団体や登録支援機関は制度運用を支える重要な役割を持ちますが、だからといって企業が受け身の姿勢でいいわけではありません。自ら法的義務を理解し、必要な対応を主体的に行うのが雇用主として当然の責任です」。
確かに、技能実習制度における監理団体や、特定技能制度における登録支援機関は、外国人労働者の受け入れから生活支援まで幅広い業務を担っている。
しかし、制度の一部は委託できても、最終的な雇用責任は企業にある。
労働条件の説明、就業規則の開示、日常的な勤務管理、定期的な健康診断の実施、職場環境の整備など、いずれも企業が自ら行うべき”基本のき”だ。
「支援機関はあくまで企業の取り組みを支援する”補助輪”の役割であり、実際にハンドルを握って方向性を決めるのは企業自身でなければなりません」と青木氏は強調する。
企業が主体性を持たずに外部機関に依存しすぎると、結果的に外国人労働者との直接的な関係構築がおろそかになり、問題が発生した際の対応が後手に回ってしまう危険性がある。
一方で、青木氏は外国人雇用に伴う課題を前向きに捉える視点も提示している。
「外国人雇用は、自社の労務管理や職場環境を根本から見直すチャンスでもあります」。
外国人労働者を受け入れることで、これまで当たり前だと思っていた職場のルールや慣行を客観視する機会が生まれ、結果として日本人従業員にとってもより働きやすい環境が整備されることが多いという。
例えば、外国人労働者への説明のために就業規則を分かりやすく整理することで、日本人従業員にとっても理解しやすい規則になる。また、労働条件を明確に文書化することで、日本人従業員に対してもより透明性の高い雇用関係を築くことができる。
さらに、多様な文化背景を持つ従業員が働く職場では、コミュニケーションの取り方や業務の進め方についても工夫が必要になり、結果として組織全体のコミュニケーション能力向上につながることも多い。
「外国人労働者の視点を通じて自社を見直すことで、これまで気づかなかった問題点や改善の余地を発見できることがあります」と青木氏は語る。
実際に、外国人労働者を積極的に受け入れている企業の中には、労務管理の精度向上、職場コミュニケーションの活性化、業務の標準化・マニュアル化の進展といった組織改善につながったケースも見られる。
4.信頼関係構築の出発点としての”入口”対応

青木氏の「外国人雇用は、自社を見直すチャンスでもあります」という言葉が示すとおり、外国人労働者との信頼関係を築けるかどうかは、雇用の”入口”でどれだけ誠実に、そして丁寧に向き合えるかにかかっている。
表面的な手続きを整えただけの形式的な受け入れではなく、相手の立場に立った説明と相互理解に根ざした対応こそが、外国人労働者の定着化と組織全体の発展につながる第一歩となる。
現在、日本で働く外国人労働者数は過去最高を更新し続けており、今後もこの傾向は続くことが予想される。人手不足が深刻化する中で、外国人労働者は日本の労働市場において不可欠な存在となっている。このような状況下で、個々の企業が外国人労働者との信頼関係をいかに構築できるかは、企業の競争力や持続可能性を左右する重要な要素となりつつある。
外国人雇用を成功させるためには、制度の表面的な理解だけでなく、異なる文化背景を持つ人々との真の相互理解が不可欠である。雇用条件の詳細な説明、職場文化の丁寧な紹介、言語の壁を乗り越える努力、そして何より相手を一人の人間として尊重する姿勢が求められる。
企業が監理団体や登録支援機関に依存するのではなく、自らが主体的に外国人労働者と向き合い、彼らが安心して能力を発揮できる環境を整備することが重要だ。
見かけだけを整えた受け入れ体制ではなく、外国人労働者一人ひとりの人生や価値観を尊重し、彼らが安心して能力を発揮できる環境を整備することが、結果として企業にとっても大きな利益をもたらすことになる。
そのためには、雇用の”入口”から真摯な姿勢で取り組むことが何よりも重要だ。
外国人雇用の成功は、制度の理解や手続きの適切な実施といった技術的な側面と同時に、人と人との信頼関係をいかに構築するかという人間的な側面の両方にかかっている。
入口での誠実な対応が、その後の長期的な信頼関係の基盤となり、企業と外国人労働者の双方にとって有益な結果をもたらすのである。
(※このコラムは、ビル新聞2025年6月23日号掲載「外国人雇用の軋轢は‟入口‟から生じる」Vol.66を加筆転載したものです。)





